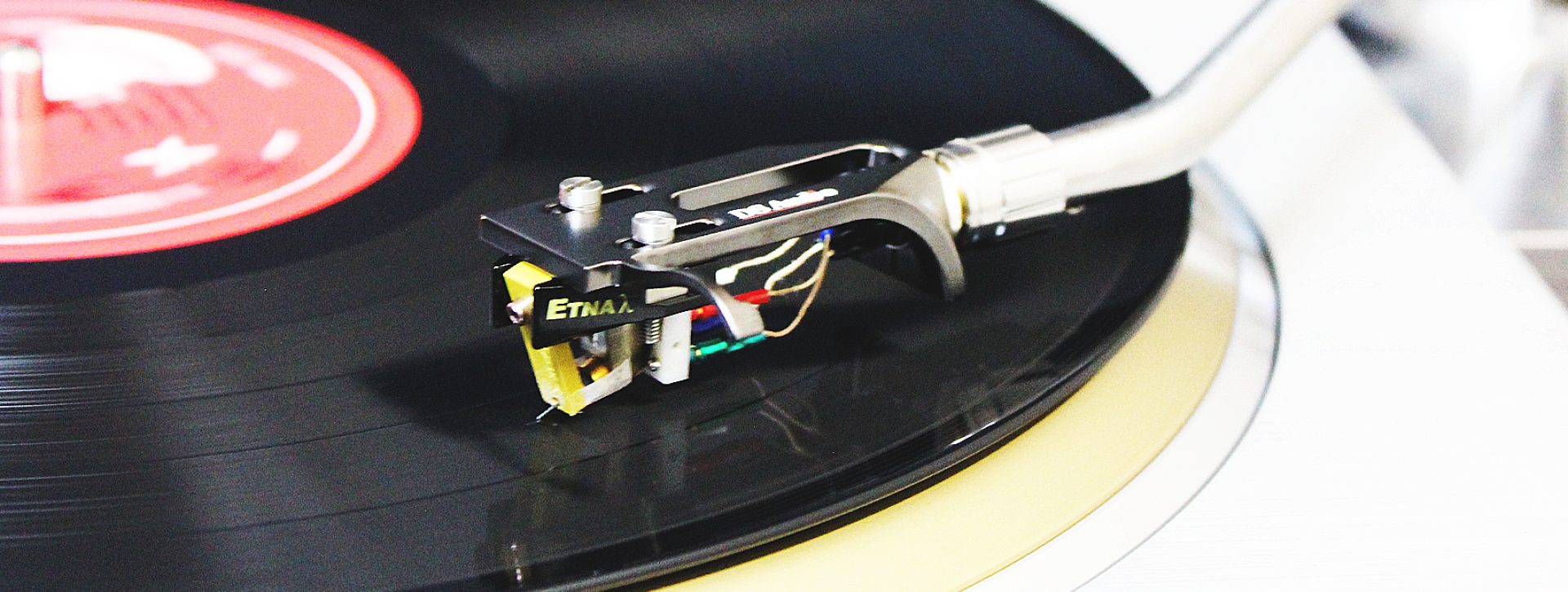先日DS Audioの光カートリッジについて近日中のレビュー予告をしたが、その前に同社の偏心検出スタビライザーES-001のレビューをしたいと思う。時間が無いので簡潔に^^。
光カートリッジ関連デモ機送付の際、ついでにということで貸し出しいただいたお品だ。

本機は端的に言うと、レコード盤の偏心を検出し手動で補正する前提の装置である。偏心があることでレコードの回転ムラ、いわゆるワウ・フラッターが大きくなり、原音忠実再生に影響を及ぼすことになる。レコードプレーヤーの性能が良くてもレコードの偏心があることですべてが台無しになるというとは無いと思うが、できる限り偏心が無い状態でレコード原音忠実再生が望ましい。ということでより良いレコード再生環境へ導く系オーディオアクセサリーということで早速使ってみた。

使い方はとても簡単で、レコードを乗せたプレーヤーのセンタースピンドルに本機を装着し(乗せるイメージ)、本体上部を手で固定しレコードプレーヤー再生ボタンを押す。すると手で固定されてる上部はそのままで、セパレートされている下の部分のみ回転し始める。本機上面の液晶パネルに測定開始ボタンが現れそれを押すと2秒ほどで測定が終了し、液晶画面に偏心度合いが表示されたらレコードプレーヤーを停止。参考動画(Youtube動画)
上記画像は測定後のイメージで、中レベルの偏心度合いにつき黄色で+マークが表示される。度合いが大きいと赤、小さいと緑で表示される。液晶画面の+がセンターにあれば問題ないが、ずれたところにある場合レコード盤を手でずらしてあげなければならない。センタースピンドルにレコードが収まっているのに、レコードをずらすって?と、当方も疑問に思ったが各レコードのセンターホール、ジャストサイズもあれば少し遊びのある物や、ゆるゆるの物もあるようで、更にセンターホール自体ずれている物もある(論外)。各レコードにより調整度合いも変わってくる。
論外はさておき、穴に余裕あればレコードを手でずらし+マークをセンターに移動することができ、最大限センターに近づけるまたは合致させることで偏心補正完了となるわけだ!穴に余裕のない物は調整のしようがないのであきらめるしかない。しかし本機の備品としてレコード盤のセンターホール拡大用のリーマー(金属の棒)が付属しており、自己責任で穴を大きくし偏心を補正することも可能となっているが、個人的にレコードに手を加えることはしたくないので、よほどのことが無い限りこれは使用しないだろう。

初めに測定したものは穴に余裕が無く測定位置が限界だったので、ほぼセンターに来ている画像を挙げてみた。本機は超精密機械で測定後の操作は手作業でアナログな手法だが、センターに配置できた時はなんだかうれしくなってしまう(笑)。さて、測定後+マークがセンター位置に近づいたところであとはレコード再生するのみ。本機自体に重量があり程よいスタビライザーとなる。

続いて音質の変化だが、中レベルの偏心度合いで偏心調整前と調整後の比較をしてみた。リアルタイム試聴では何となく定位がまとまったかな、なるほどいい感じ!というのが率直な感想だ。この感じを文章でまとめられない点はもどかしいが(笑)、間違いなく原音忠実再生に近づいていると感じた。早速録音ファイルで比較した。波形的には大きな違いはないがAB比較ツールを使いリアルタイムで比較しても同様の感想だ。ちなみに偏心調整前の回転ムラは聴感上全く感じなかった。
資金が潤沢ならすぐに購入したいと思ったが、このES-001はかなり高額である。全てのレコードに対し確実に偏心補正できるなら即買いであるが、センターホールの大きさ次第というところが引っかかる。物によっては補正ができない場合があるし、補正しても中レベル補正程度の場合もある。原音忠実再生したいからと言ってリーマーで穴を大きくしてまで偏心補正したいとは思わない。よって購入することはないが、いつか資金に余裕ができた時、購入再考も有りかなと。

今回ES-001をデモしたことで偏心やワウ・フラッターについて改めて考えたが、いずれも意識しなければ音の違いや変化がわからないということ。偏心調整前と調整後の音も何も知らされてない状態だと恐らくわからないと思う。また、ワウ・フラッター回転ムラについても、DJ用トラックをベルトドライブ方式のレコードプレーヤーで再生録音したデータを解析したところ、驚くほど回転ムラがあったが聴感上わからなかった経験があり、それを踏まえた上で改めて聴くと何となく違和感がある程度であった。そんな経緯からダイレクトな音の変化が(高音質化)わずかしか感じ取れなかった本機、導入に前向きになれないというのが結論だが、実はレコード忠実再生において偏心補正は重要なファクターなのかもしれない。そしてレコードデジタルラボには必要なのかもしれない。先日(2回に分けて)デモ試聴した第三世代光カートリッジの衝撃(高音質化大躍進)が強すぎて、目先の高音質化に目が眩み、購買意欲がそっちに偏り過ぎていることが盲目の原因か、、、、。本来なら、ES-001を先に導入すべきでは?葛藤している自分が居る^^。さてどうするか。